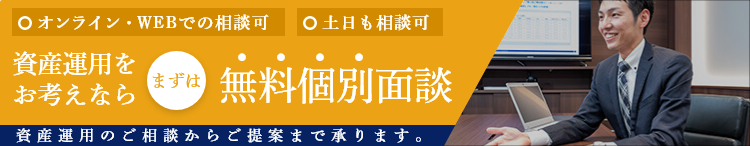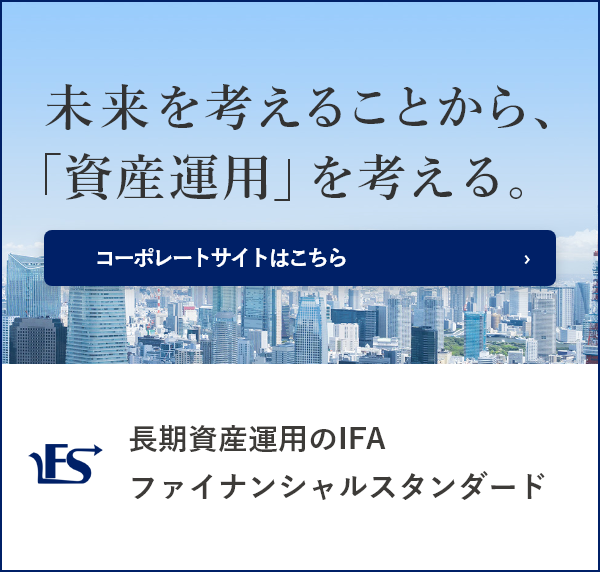子会社が親会社を追い抜いたケース
1.はじめに
欧米と比較して封建的な慣行が残る日本の企業社会では、社内の上下関係のみならず企業間の系列や親子関係においても縦社会の色合いが出やすいものです。このため、日本の企業社会では系列企業間の序列に変化が起こりにくく、特に親子関係にある企業では顕著です。
なぜなら、日本の経営者や従業員は親会社・子会社の序列に対する拘りが強いことから、親会社の立場であればメンツや優越性維持の観点から子会社の台頭を資本の論理などを駆使して封じ込んでしまう傾向があるからです。また、子会社であるために制約されがちな事業拡大も、子会社の可能性を狭めることになっています。
このような状況では、日本で子会社が親会社を追い抜く下剋上が起こるということは考えにくいでしょう。実際にサラリーパーソンとしての経験がある人ならば、このことを実感したことがある人は多いと思います。
一方で、日本でも子会社が親会社を追い抜いたという実例は少なからず存在します。そして、親会社を抜いた子会社の中には広く社名の知られた企業もあるのです。
本コンテンツでは、その実例をご紹介するとともに親子逆転が起きる背景についてご説明します。
2.子会社が親会社を追い抜いた実例
ごく一部ですが、以下でその実例をご紹介します。なお、何をもって子会社が親会社を逆転したかについては議論がありますが、本コンテンツでは上場企業であれば時価総額、非上場企業であれば売上高を尺度とします。
①トヨタ自動車(親会社:豊田自動織機)
言わずと知れた、日本最大の企業です。織機(布製品を織る機械)の製造から出発した豊田自動織機の自動車部門として1937年に設立され、戦後の高度経済成長期の追い風と確固たる技術に裏付けられた生産力を背景に、幾度かの危機を経験しつつも世界有数の自動車メーカーとして君臨し続けています。豊田自動織機の時価総額が約1兆8410億円に対してトヨタ自動車は約21兆5740億円ですから、その逆転振りは歴然です。
なお、信託銀行や自社株を除くと現在でも筆頭株主は豊田自動織機(7.0%)ですが、買収防衛の観点からトヨタ自動車も豊田自動織機の23.5%を保有する筆頭株主となっています。
②セブンイレブン・ジャパン(親会社:イトーヨーカ堂)
現在は元親会社の大手スーパー・イトーヨーカ堂とは持株会社であるセブン&アイ・ホールディングスの100%子会社として並列関係にありますが、もともとは1973年にイトーヨーカ堂の既存子会社が米国セブンイレブン社から営業ライセンスを取得し、コンビニエンスストアとして業態転換したことに端を発する企業です。その後は日本の市場に見合った営業形態を確立させコンビニエンスストア最大手として地位を盤石なものとし、売上高ではイトーヨーカ堂にダブルスコアをつけるまでに成長しています。
なお、1991年にセブンイレブンとしてのライセンス元である米国企業をイトーヨーカ堂とともに買収・子会社化しており、大きな話題を呼んでいます。
他にも、ダイセル(直近の時価総額は約4,472億円)から独立した富士フイルムホールディングス(同、約2兆3,330億円)、富士通(同、約1兆4,666億円)から独立したファナック(同、約3兆8,767億円)、古河機械金属(同、567億円)から独立した古川電気工業(同、2,307億円)があります。
3.なぜ、子会社は親会社を追い抜けたのか
上記のように親会社を抜いた企業の多くに共通していることは、優れた経営施策や企業努力があったことはもちろんのこと、子会社としてのコアビジネスがその後の時代のニーズに合致していたということです。
例えばセブンイレブン・ジャパンは市民生活の夜型化を捉えたものですし、ファナックは産業のデジタルオートメーション化を捉えたものでした。ある事業を子会社として分社化することは、当該事業が会社のコアビジネス足り得ないとの判断から為されることが多く、その意味では親会社が時代を読むことができなかったことも一因といえます。
また、ビジネスが軌道に乗り出した子会社の経営に対して、親会社が下手な手出し・口出しをしない会社ほど伸びている傾向があります。たとえ親会社からであろうと必要以上に外部の指図や支援を受けず、独立独歩で経営していくことこそ企業としての成長につながるという定説が、ここでも証明されています。
4.まとめ
弛まぬ企業努力に裏付けられた実力があり、さらに時代背景が味方すれば、子会社が親会社を追い抜くことは日本でも十分にあり得るのです。特に産業革命のようにデジタルテクノロジーが既存の産業を凌駕することが予想される近い将来は、親子会社の規模・地位逆転は珍しい話ではなくなるのではないでしょうか。