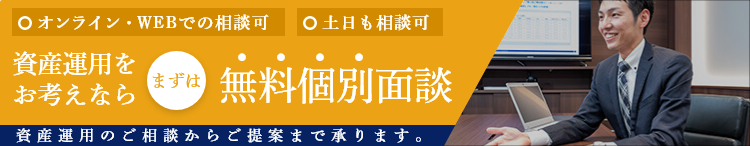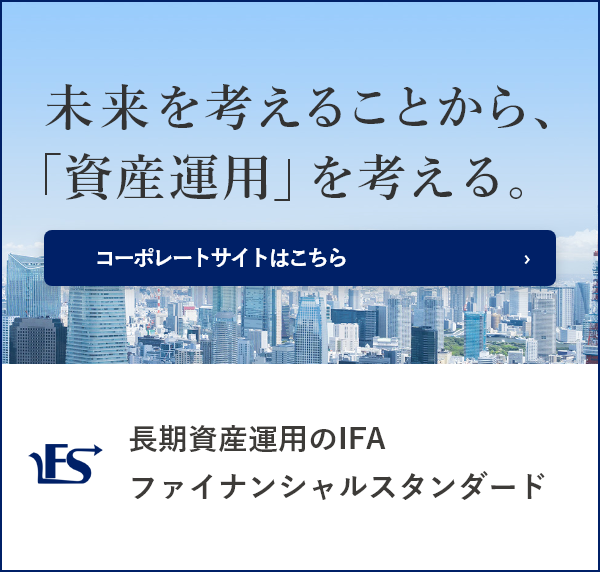相続対策に影響有り!?「配偶者居住権」を優しく解説
はじめに
2018年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、相続関係に関する法律が一部見直されました。本改正における論点は多々ありますが、そのうち本コンテンツでは「配偶者居住権」をクローズアップし、その概要についてご説明します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、ある人が亡くなり相続が発生した際に、亡くなった人の自宅建物に居住している配偶者が亡くなるまで引き続き居住する家を確保できるようにすることと、居住権という考え方の導入で相続税評価額の引き下げを行い配偶者が預貯金など今後の生活資金を多く確保できるようにすることを目的に制定されました。この制度は新民法1028条として、2021年の施行後に配偶者が亡くなった場合に適用される予定です。
この適用要件としては、相続発生時に配偶者が亡くなった人の建物が対象であること、配偶者が配偶者居住権を取得するためには遺贈(亡くなった人が配偶者に自宅建物を取得することを遺言で定めており、それを事由に配偶者が自宅建物を取得すること)や遺産分割(他の相続人と亡くなった人の遺産を分けること)によるものであること、配偶者居住権の譲渡は認められていないことが挙げられます。
配偶者居住権が制定された背景
例えば、亡くなった人の遺産が自宅(4,000万円)と銀行預金(6,000万円)の合計1億円で、それを配偶者と子2人で分けることを考えてみましょう。
現行の民法で定められた法定相続割合は、配偶者が2分の1で、2人の子がそれぞれ4分の1ずつ取得することになります。仮にこの割合で分割した場合、配偶者が自宅を取得すると銀行預金は1,000万円しか取得できなくなるため、今後の生活費に不安が出てしまいます。一方で、銀行預金を5,000万円取得した場合は住む家が無くなってしまいます。
そこで、配偶者に配偶者居住権が2,000万円認められたことを想定してみましょう。
同じく法定相続割合で分割した場合、配偶者が取得する遺産は配偶者居住権2,000万円と銀行預金3,000万円、子がそれぞれ取得する遺産は自宅の負担付所有権(居住する権利の無い所有権)1,000万円と銀行預金1,500万円となります。
結果、配偶者は引き続き亡くなった人が遺した自宅に住む権利と現行民法よりも多くの銀行預金を取得することができるのです。
遺産全体における不動産評価額の割合は高くなることが一般的であるため、現行の民法下では自宅建物を取得すると他の遺産が取得できなくなることが往々にしてあるのです。特に亡くなった人の配偶者は高齢であることが多く、特に人生100年時代における今後の余生はますます長くなるケースが多くなることが想定されることから、配偶者の住居と生活資金に一層の配慮が必要との見解から今回の民法改正に至ったのです。
相続税対策に影響は?
現状、配偶者居住権の評価方法は法制審議会民法(相続関係)部会が示している「簡易な評価方法」で算出することになります。
具体的には自宅の現在価値から負担付所有権の価値を差し引いたものが配偶者居住権の価値となりますが、理論上は負担付所有権の分だけ配偶者が事実上取得する自宅の評価額を圧縮しているため、その分節税できていると考えられます。もっとも、多くの場合は1億6,000万円の配偶者控除の範囲内に納まると考えられ、現実は相続税の発生そのものが限定的でしょう。
一方、配偶者居住権は配偶者一代限りで消滅しますので、子が配偶者居住権を相続することはなく当然に相続税も発生しないと考えられています。言い換えると、当初の相続発生時に自宅を負担付所有権として相続していた子は、配偶者の相続発生時に追加の相続税の負担無く負担付所有権が完全所有権となるのです。つまり、配偶者居住権の分だけ相続税評価額が圧縮されたことになり、相続税対策の一環として活用することも可能と考えられます。
まとめ
配偶者居住権は、2021年までその算定方法や税金面の取り扱いなどの面で様々な施行細則などが出てくると考えられます。特に相続対策として有効に機能するかについては、今後出てくる指針などをよく考慮しておく必要があります。また、本件に限らず相続対策については税理士やファイナンシャルプランナーに相談しながら進めることをお勧めします。