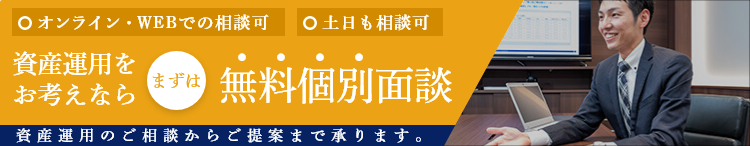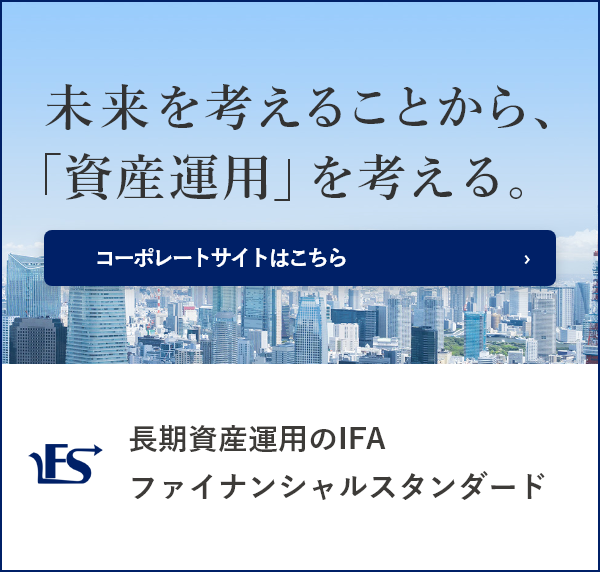2019年は日経最高値から30年 最安値から10年 ファンダメンタルから考える相場の異常値
日経平均株価を語る上で、記録に残るのが最高値38,915.87円を記録した1989年、バブル後最安値7,054.98円を記録した2009年です。
いずれも極端な数値であるかも知れませんが、直近の株価と比較してその時代の企業業績や市況環境を考慮すると本当に異常値だったのでしょうか?検証してみましょう。
用いる指標について
日経平均株価の絶対値の高低だけでは、そのときの日経平均株価が他の時点と比較してどれだけ割高か、割安かを検証することはできません。株価は最終的に投資家の需要・供給によって決まりますが、同時に企業の業績を映し出す鏡でもあるので日経平均株価の構成銘柄の業績などを反映した指標を用いて検証することが妥当です。
株価の割高感・割安感を計測する指標は数多くありますが、本コンテンツでは代表的な指標であるPERとPBRを用います。
PER(Price Earnings Ratio)とは株価収益率のことで、株価を1株当たり当期純利益で割って計算します。これにより1株あたりの何倍まで株が買われているかがわかり、過去のPERよりも高ければ株価は割高水準にあることがわかります。
PBR(Price Book-value Ratio)とは株価純資産倍率のことで、株価を1株当たり純資産で割って計算します。純資産とは、企業が保有する全資産から負債を差し引いたもので、自己資本または株主資本ともいわれます。そして、1株当たり純資産とは純資産を株式数で割ったもので、これが大きければ大きいほど割高ということになります。PBRが1倍であるということは、株価が資産価値と同水準であることを意味します。すなわち株価の割高感・割安感はPBRが1倍を超えているか否かでみることができます。
なお、2019年1月31日の日経平均株価は終値20,773.49円・PER12.06倍・PBR1.10倍です。
1989年の日経平均株価
バブル崩壊のときは間近に迫っていたものの、世間はそれに気づかずバブル景気を謳歌していました。財テクブームも最盛期であり、投資マネーの格好の振り向け先だった株式は天井知らずともいえる値上りを見せ、「株価は絶えず上がるもの」という神話まであったのです。
1988年末の大納会で30,159.00だった日経平均株価は1989年12月28日の大納会で38915.87円と、実にプラス29パーセントもの値上りをみせました。そして、1989年大納会の株価は、日経平均史上最高値として記憶されることになります。
この日の株価はPERが61.74倍、PBRが5.57倍でした。先述した2019年1月31日の株価と比べると、いかに買われ過ぎだったかということがわかります。
2009年の日経平均株価
2009年の大発会は前年大納会比183.56円高の9,043.12円と、2ヶ月ぶりの9,000円台を回復し大いに市場参加者を安心させました。
前年に発生したリーマン・ショックから立ち直るために、2009年は世界的に大規模な金利引き下げが行うなど、各国が協調して経済政策に取り組む動きが見受けられました。
3月には引値ベースでバブル後最安値7,054.98円、11月にはドバイ・ショックが起きたものの、大納会は10,546.44円と前年の大納会比プラス19.04パーセントで引けました。リーマン・ショックからの回復に自信が持てない市場参加者が多かった中、少しずつ良い方向へ歩みだした年といえるでしょう。
2009年大納会の株価のPERは35.82倍、PBRが1.30倍でした。2019年1月31日と比べると日経平均株価は半分程度の水準であるにもかかわらず割高ということになりますが、PERは株価を1株当たり当期純利益で割って計算するため、利益が減少する景気後退期にはPERは高くなってしまう傾向があります。
株価の割高割安を判断するのに万能な指標はなく、「景気後退期にPERはあてにならない指標」という専門家も多いのです。
まとめ
過去の経験則で一般的に、PERの適性値は15倍前後、PBRの適性値は1倍といわれています。そのように考えると、日経平均株価は1989年はもちろんのこと2009年も実は買われ過ぎだったということになります。しかし2009年の場合には、その後の企業業績の回復を背景にPERは低下していきました。
万能な指標がないため、「バブル」や「景気の底」は分かりづらいのです。あとになってみて「あの時はバブルだった、あの時は異常に安かった」ということがわかるのです。高値掴みを回避するために、各指標の特徴や限界を見極めながら判断をしていく必要があるのです。