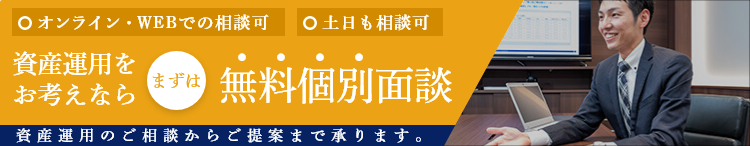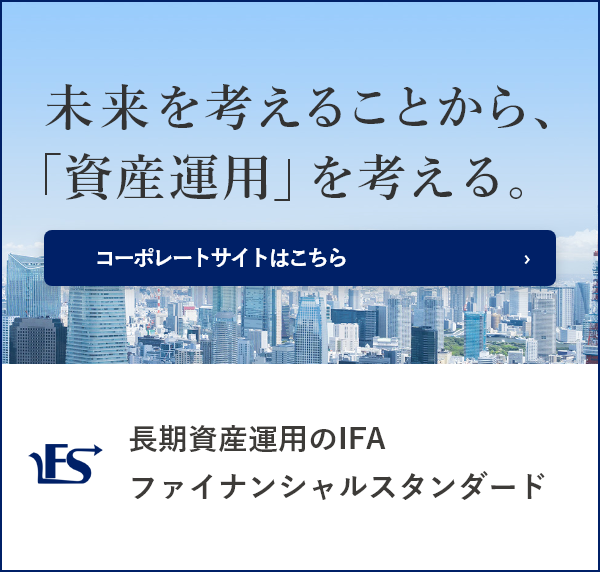税制大綱の隠れた目玉 「相続時精算課税制度」の変更点を解説する
令和5年度の税制改正大綱が昨年12月に閣議決定されました。その中で、隠れた目玉として「相続時精算課税制度」の改正があります。その背景には、生前贈与に対する規制の強化があります。
そこで、今回は、生前贈与の規制強化の内容と相続時精算課税制度の変更点について解説します。
生前贈与の規制強化の内容
被相続人(亡くなった人)が資産家の場合、相続人に莫大な相続税が発生するため、被相続人が生前のうちに相続税対策が行われるのが一般的です。その方法の1つとして「生前贈与」があります。
生前贈与は、文字どおり生前に相続人などに財産を贈与しておくというものです。
生前に財産を無償で移転した場合、相続税の税率よりも高い贈与税が発生します。
ただ、贈与税には、110万円の基礎控除があるため、年間110万円までは非課税になります。これを利用して、たとえば、5人に110万円ずつ贈与すれば、550万円の財産を非課税で移転することができます。これを複数回繰り返せば、多くの財産を非課税で相続人らに移転できるわけです。
ただ、亡くなる直前に贈与して相続税を回避することは妥当ではないことから、亡くなる日から遡って3年間になされた生前贈与は相続財産に加算するという「生前贈与加算」があります。この年数が今回の改正で7年間に延長されることになりました。つまり、生前贈与による相続税対策に対して規制が強化されたわけです。
相続時精算課税とは?
生前贈与をした場合に贈与税を回避する手段としては、110万円の非課税枠を使う方法以外に相続時精算課税を使うという方法もあります。相続時精算課税は、生前贈与をした場合に2,500万円までは贈与税を課さないというものです。その代わり、生前贈与した額は、相続時に相続財産に組入れられます。相続時精算課税を利用するためには税務署に届出が必要になります。
なお、相続時精算課税を利用するためには、①贈与者が贈与をした年の1月1日現在で60歳以上であること、②受贈者(贈与者の直系卑属である推定相続人または孫)が贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上であること、という2つの要件を満たす必要があります。
相続時精算課税は、贈与税がかからないだけで、相続税の節税にはならず、また、宅地等の評価を下げることができる「小規模宅地等の特例」が使えなくなるなどのデメリットもあるため、これまではあまり利用する人がいませんでした。
しかし、生前贈与の規制強化に付随して相続時精算課税の内容が改正されることになったため、今、注目を集めています。
相続時精算課税の変更点
なお、相続時精算課税を利用するためには、①贈与者が贈与をした年の1月1日現在で60歳以上であること、②受贈者(贈与者の直系卑属である推定相続人または孫)が贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上であること、という2つの要件を満たす必要があります。
既に説明したとおり、これまでの相続時精算課税は、贈与税がかからないだけで、相続税の節税にはなりませんでした。しかし、今回の改正で、相続時精算課税を選択した場合には、年間110万円までは課税されないことになりました。
つまり、相続時精算課税を選択することで、これまでと同様、年間110万円の範囲内であれば非課税で生前贈与ができるようになったということです。しかも、相続時精算課税の利用者は、「生前贈与加算」と無関係なため、死亡前7年間になされた生前贈与でも相続財産に加えられることはありません。
まとめ
今回の税制改正大綱では、「相続時精算課税」の改正がありましたが、生前贈与に対する規制を強化した分、相続時精算課税は、優遇措置が認められるようになり、結果的に相続時精算課税を利用することで、これまでと同様の優遇を受けられることになりました。
ただ、相続時精算課税を選択すると、永久にこの制度に拘束されます。また、贈与をするごとに税務署へ届出が必要になります。さらに、建物などの場合、時間の経過と共に資産価値は下がるものですが、相続時精算課税を選択した場合、贈与した時点の時価で評価されるため、相続時に資産価値が下がっていても考慮されないなどのデメリットもあります。
したがって、相続時精算課税を選択するかは慎重に判断する必要があります。